1 裁判の概要
東京地裁民事第6部に係属 裁判長高橋利文
(1999年12月より異例の5人合議体制)
(1)提訴
| 1996年 5月31日 |
第1次提訴(原告102名) |
| 1997年 6月 3日 |
第2次提訴(原告110名) |
| 1998年10月16日 |
第3次提訴(原告115名) |
| 2000年11月16日 |
第4次提訴(原告191名) |
|
(原告数合計) 518名 |
現在第5次提訴の準備中
(2)原告
都内23区に居住または通勤していて、気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺気腫のいずれかの病気を発病した患者またはその遺族。第3次以降では、多摩地域の主要幹線道路の沿道で発病した患者を含む。未認定患者を原告に加えた初めての裁判。未認定患者の数一次14名、二次16名、三次61名、四次97名(合計)188名
(3)被告
国、首都高速道路公団、東京都
ディーゼル車を製造している自動車メーカー7杜(トヨタ、日産、三菱、いすず、日野、日産ディーゼル、マツダ)
(4)請求の趣旨
1)汚染物質の排出差止め
2)損害賠償講求額1次20億円、2次21億円、3次29億円、4次47億円(総計117億円)
(5)請求の原因
i)国・首都高速道路公団・東京都一道路から発生する大気汚染につき幹線道路の設置管理者としての責任
ii)国・東京都一公害の規制(排ガス規制、交通規制)を怠ってきた責任。
iii)メーカー一排ガス対策を怠って、汚染物質を大量に排出する自動車を製造販売してきたことは不法行為。
2 裁判の経過
1996.9.24 第1回口頭弁論
1997.9 総論立証開始
(総論立証の内容)
| 論点 |
原告申請証人 |
被告申請証人 |
| 発病の因果関係 |
福富和夫(もと国立公衆衛生院統計学部長) |
I.B.テーガー(カリフォルニア大学バークレイ校) |
| 到達の因果関係 |
青山貞一(環境総合研究所所長) |
なし |
| 道路管理者の責任 |
福川裕一(千葉大教授・ 都市工学) |
なし |
|
水谷洋一(静岡大助教授 ・環境政策論) |
| メーカー責任 |
水谷洋一(静岡大助教授・環境政策論) |
高木靖雄(日産自動車)、蠣崎客(日野自動車) |
| 国の公害規制責任 |
水谷洋一(静岡大助教授・環境政策論) |
斉藤孟(早稲田大学名誉教授) |
2000.5各論立証(原告本人尋問)
2001.7総論につき原告側最終準簿医書面提出
2001.12.18最終弁論・結審
(開いた法廷の回数)46回
判決時期2002年夏〜秋
3 裁判の目指すもの
①大気汚染の原因者(主要には自動車メーカー)の責任で被害者救済制度の確立
②東京から自動車排ガス公害の根絶
・ディーゼル規制の一層の強化。メーカーの責任による排ガス削減策の徹底。
・道路交通総量削減策の強化(ロー一ドプライシング、車に頼らぬ街づくり)
・さらなる環境悪化の原因になる幹線道路の建設ストップ
1 大気汚染公害被害の特徴
身体的被害(病気の苦痛、難治性、死の恐怖、副作用)
日常生活の被害(睡眠の妨害、日常生活の困難)
家族生活の被害(家族の負担、家庭不和、結婚・出産の困難)
経済的被害(経済的困窮、仕事上の不利益、就職の困難)
社会生活上の被害(働きがいの喪失、交友関係の喪失、学業の困難)
精神的被害(生き甲斐の喪失、引きこもり、周囲の不理解、うつ病)
⇒人生総体としての被害
2 未認定患者の被害の特質
(1)未認定患者とは
昭和63年3月、公害健康被害補償法(S49年9月施行)による新規公害認定打切り→それ以後に発病した者、発病していても公害認定を受ける機会がなかった者は公害認定を受け得なくなった。
公害認定がなされれば受けられたであろう給付療養の給付(医療費)、障害補償費(損害の填補=生活保障)、児童補償手当、療養手当(入院雑費、通院交通費)、遺族補償、葬祭料など
第1次原告12名について、得べかりし紛付額を試算
成人男性 1782万円〜5833万円
女性 1474万円〜3736万円
児童 897万円
(2)未認定患者の被害
著しい経済的困窮が被害をより一層深刻なものとしている。
①深刻な医療費負担
②医療の抑制・入院の回避
③無理な就労による疾病の増悪
④著しい生活の困窮・家庭生活の破壊
⑤生活保護に頼らざるを得ないことの精神的苦痛、屈辱感
3 新しい公害被害者救済制度を
(1)基本的な考え方(我々の提案)
①原因者負担自動車排ガス公害の原因者として例えば
自動車メーカー(7割)、石油メーカー(1割)、道路管理者:国・自治体・公団(2割)とすることも? 道路特定財源からの支出も検討すべき。
②賦課基準
自動車メーカー負担分については、前年に販売した自動車の汚染物質排出総量の比率で配分(排出削減へのインセンティブを考慮)
③制度枠組み
公健法と同様の認定要件(指定地域内に一定の期間居住または通勤)と被害の完全回復にふさわしい給付水準(少なくとも現行公健法と同水準)を確保すべき
④地域指定
一定濃度(例えばSPMについては名古屋の差止基準である年間98%値0.1mg/㎡、N02については旧環境基準の2倍である2%除外値0.04pp㎜)を超える測定局のある行政区は面的に指定。
その他の地域については幹線道路の沿道を指定。
⇒東京では23区及び多摩東部は面的に指定されることになろう。
(2)制度の実現を目指して
1)東京都の動き
東京都は2000年3月、18歳未満の公害病患者に対する医療費助成条
例の一部改正に当たって「大気汚染の原因者の責任を明確にしたうえで、原因者責任と適正な負担の在り方」やその他、制度全般を見直していくという方針を掲げ、都議会でも同旨の付帯決議がされている。しかし現在のところ「適正な負担」をさせるべき「原因者」をどう確定するかについて、東京都は明確な態度を示しきれていない。
2)東京大気裁判と被害者救済制度来る東京大気第1次判決において
①東京の大気汚染公害の原因者として自動車メーカーは被害救済の責任があること
②被害者の救済は一刻も猶予し得ない杜会的な課題であることを明らかにした判決が下されるなら、救済制度実現に向けて大きな力になることは明らか。原告団は、被害者救済制度の確立を東京都との全面解決のための最も重要な条件と位置づけて、勝利判決を機に、東京都に対し早急に公害被害者の救済制度を作っていくことを強く求めていくことにしている。
自動車排ガスによる健康被害(気管支ぜん息・肺気腫・慢性気管支炎)について、自動車メーカーの法的責任が認められるか否か。この点は初の司法判断となる。
I 原告の基本的主張
被告メーカーらは、遅くとも1960年代後半には白動車排出ガスによる本件疾病を初めとする健康被害を予測しえていたにもかかわらず、大気汚染物質低減対策が不十分な公害自動車を長年にわたって大量に製造・販売し続けてきた(とりわけ1970年代後半以降ディーゼル車の製造・国内販売の比率を飛躍的に高めてきた)結果、原告らの生命・健康に重大な被害を与えたものであり、民法709条・同719条(不法行為)の責任を負う。
Ⅱ 主要な争点
1 被告メーカーの故意・過失〜その1、ディーゼル化の推進〜
(1)ガソリン車選択義務違反
①公害対策上はガソリン車が優位
→深刻な大気汚染の発生が予見される場合には、技術的にガソリンエンジンが搭載可能な車種にはガソリンエンジンを選択し、ガソリン車を製造販売すべき義務がある。
②ところが被告メーカーらは、1960年代後半以降普通トラックの分野で、また1970年代後半以降は小型トラックの分野で、急速にディーゼル化を推し進め、その結果本件地域の大気汚染を一層深刻化させた。
③現在生産されているデイーゼル車のうち、7〜8割の車種はガソリンエンジンで代替が可能車両総重量15トンクラスの大型トラックまでガソリンエンジンの搭載が技術的に可能であることは被告申請の斉藤証人も確認
(2)ディーゼルメリット論
a 被告メーカーの主張
①ディーゼル車には燃費・性能面でガソリン車よりも優位。ディーゼル化の進行は消費者の需要に応えた結果であり、不当なことではない
②ディーゼル車はC0
2排出量の問題で地球環境問題に役立つ
b ディーゼルのメリットは軽油優遇税制に由来する経済性の問題に帰着
*70年代後半に税率格差が大幅に拡大。軽油とガソリンの価格差は50円以上に。→そこで一気にデイーゼル推進を企業戦略に。
現在もトヨタ、日産はガソリン普通トラックを大量に製造(両者が製造した普通トラックの70%はガソリン車である)。ところがそのガソリントラックは全て輸出用であり、国内では全てディーゼルトラックを販売している。
→海外では軽油よりガソリンの方が安いところが多く、またディーゼルに対する規制が厳しいことから、ガソリン車の方が売りやすい=要するに「どちらがたくさん売れて儲かるか」だけを基準に売り分けているのが実態。「性能ゆえディーゼル化進行」との主張の欺嚇性は明らか。
c 地球環境問題はディーゼル化推進を正当化しえない
・東京都「ディーゼル車NO作戦ステップ2」
「地球温暖化防止のために、二酸化炭素排出量の抑制は東京にとっても重要な課題である。しかし、大気汚染が深刻な状況にある東京では、地球温暖化対策を理由に現在のディーゼル車を増加させるべきではなく、2酸化炭素排出量の抑制は自動車交通量自体の削減、都市活動全体の省エネルギー化によって達成すべきである。」
・被告申請の斉藤証人もC0
2対策はガソリン車の燃費改善により解決すべきで、ディーゼル車への転換促進の理由にならないと証言
2 被告メーカーの故意・過失〜その2公害対策の憐怠〜
(1)被告メーカーの主張(技術的不能論)
「自動車メーカーは、各時代ごとに可能な限り最大限の排ガス低減措置を講じて単体規制をパスしてきた。それ以上の排ガス低減はもはや技術的に不可能であったのだから責任はない。」しかし実際には、経済性や運転性能の低下を嫌い、また製造コストの高騰を嫌って、技術的には可能な排ガス低減技術を採用してこなかった事実が、審理の中で多数明らかにされている。以下いくつかの例を紹介。
(2)直噴化の推進
・経済効率では直噴式が有利。他方公害対策では副室式が有利。そこで、1970年代前半「排ガス対策を取りやすい副室式を基本にすること」が中公審の基本政策であった。
・副室式であれば大幅に排ガス低減が大幅に可能であることを知りながら、被告メーカらは副室式から直噴式へのシフトを推進(直噴式の方が排ガス規制も甘かった)。
・技術的には直噴化が難しいとされた中小型トラックまで技術開発を進め直噴化を推進。中型トラック(車両総重量3.5トン〜8トン)の直噴式エンジン比率1979年28%→89年には91%へ
⇒経済効率(売りやすさ=会杜利益に直結)を公害対策に優先
(3)最新技術の採用見送り・出し惜しみ
・電子制御燃料噴射装置(シリンダー内への燃料の噴射の量とタイミングを、運転状態の変動にあわせてきめ細かく電子的に制御する技術で、従来の機械式燃料噴射装置に比べ圧倒的な排ガス低減効果が認められた)
1981年には実用化された技術であるが、1999年に至っても約半分の機種にしか搭載されていない。
日本ではディーゼル車の排ガス規制が緩いため、このような高度な技術を搭載しなくても規制をパスできたため。
*メーカーの技術開発担当者は「電子制御に頼ることなく平成6年度排出ガス規制をクリアすることができた」と証言
⇒電子制御はコストがかかる。規制さえパスできればコストをかけたくないとの態度で一貫している。
・その他、1970年代末のガソリンエンジンにおける三元触媒システムの搭載など様々な事実が明らかにされている。
(4)国内車と輸出車のダブルスタンダード
・裁判の中で明らかにされた極秘資料(いす“の国に対する報告書)
①1986年報告書によると、同じ型式のディーゼルエンジンでもカリフォルニア向けのモデルでは、」燃料噴射時期遅延とその関連技術の違いにより、国内向けモデルよりも,NO
xを30%削減
②1994年報告書によると、米国向けには電子制御燃料噴射装置、酸化触媒システムなどの高度な技術を搭載。
⇒規制の緩い国内向けには、公害対策よりもコスト削減を重視
*2001年12月の東京都税制調査会答申は、「国内自動車メーカーには、より規制の厳しい海外向け仕様と国内向け仕様とを分けて生産、出荷している実態があるなど、技術力があるにもかかわらず、環境負荷の小さい低公害の自動車の生産のためにぎりぎりの努力をしているとは言い難い」などとして白動車メーカー課税を打ち出している。
3 本件地域への自動車の集中と被告メーカーの責任(侵害行為論・因果関係)
(1)被告メーカーらの主張(コシトロール不能論)
本件地域の大気汚染は、自動車が本件地域に大量に集中した結果白動車排ガスが集積したことにより生じたものであるが、自動車メーカーは自動車を製造・販売したのみで、販売した自動車がどこを走行するかコントロールはできない(ユーザーの行動だから)。よって製造販売行為は違法行為とはいえないし、《販売→自動車交通の本件地域内の集積→大気汚染》という因果関係もない。自動車排ガスの集積を緩和するのは、国、地方公共団体の責任であり、自動車メーカーはその立場にない。
(2)被告メーカーの主張の誤り
①本件地域への自動車の集積はユーザーの個別意思によって左右されない本質を持つことを意図的に無視個々のユーザーの意思がどうであれ、必然的に本件地域に大量の白動車交通が集中し、排ガスを集積させるという社会構造が現実に存在している。つまり大量に自動車を販売すればその一定割合は本件地域内を走行することは客観的な事実であり、《自動車の大量販売→本件地域への自動車の集中促進》との因果関係は明らか。
②かかる杜会構造は30年以上にわたり継続しており、被告メーカーも十分に認識していたことが明らか。また自動車排ガスが大都市における深刻な大気汚染をもたらす危険があることは、遅くとも1960年代には自動車メーカーは認識していた(この時期には自動車工業会などにより、多数の調査・研究が行われていたことが裁判でも明らかにされている)。
③被告メーカーの製品が備えるべき安全性能は、大量の自動車が集中する本件地域の状況を基準とすべき本件地域には大量の自動車が集中する特性があり、また深刻な大気汚染が発生している以上、・被告メーカーらが販売する製品は本件地域における安全基準(大気汚染をもたらさないこと)を満たすものである必要がある(本件地域以外しか走行できないような自動車など販売されていない)。
④然るに被告メーカーらは大気汚染物質の低減対策が不十分なままの公害自動車を大量に製造して国内向けにこれを出荷してきた。
とりわけ1970年代後半以降、ガソリン車と比べて有害物質の排出量が格段に多いディーゼル自動車の製造販売を飛躍的に拡大し続けて、本件地域の大気汚染の更なる悪化をもたらした。メーカーらの「コントロール不能論」は自らの責任をユーザーや行政などに転嫁しようとするもので、許されない。
1 主要な争点
(1)1960年半ばから自動車排ガスによる大気汚染(NO
x,PM)による被害が深刻化していた事実を被告国が認識していたと認められるかどうか
(2)被告国がそのような国民の健康・身体・生命に対する深刻な被害を認識していた場合、適切な排ガス規制を実施して自動車排ガスによる被害を防止すべき義務(適切な時期に適切な排出ガス規制値を定めて規制を実施する義務)があるといえるか(排ガス規制の内容は国の裁量の範囲内というのかどうか)。
(3)被告国は上記排ガス規制の義務を怠ったといえるのかどうか。
2 大気汚染の深刻化と被告国による認識
以下のような事実から見て、被告国は遅くとも1960年代半ば以降、自動車排ガスによる大気汚染が人の身体・生命に重大な被害をもたらしている(あるいはもたらすおそれが高い)ことを十分に認識していたことは明らか。
(1)白動車排ガスによる健康被害は、アメリカやイギリスにおいては古くから社会問題になっている(特に1940年代のロサンゼルススモッグ事件は日本でも大々的に報道されている)。
(2)わが国においても、都内の主要幹線道路の自動車交通量は1950年代後半から飛躍的に増加し、各地で交通渋滞が頻発している。被告国は白動車産業を手厚く保護し、1960年には首都高1号線建設開始、以後続々と道路が建設されている。
(3)それにともなって、自動車排ガスによる大気汚染が杜会問題となる。新聞でも、自動車排ガスによる被害の記事は年々増加している。1960年代からは、各団体により、NOx,PM等の実測調査や沿道住民の健康調査が行われている。
(4)1960年代はじめより、NO
xやPMが呼吸器疾患の原因となることやPMの発ガン性等について、多数の研究調査報告がなされている。
3 裁量論の否定
近時の判例理論では「人の生命身体という至上の法益が侵害されようとしている場合、その危険が明白で国の規制権隈発動により回避しうることが明らかな場合、規制権限発動'すべき義務あり」。本件ではこの点からも裁量の余地なし。
4 被告国の規制義務違反
被告国は、1972年中公審答申の中で自ら「技術的に可能な限りもっとも厳しい許容限度値の設定を行うべき」とした。しかし現実には技術的に可能な水準を大きく下回る甘い規制しか実施してこなかった。
(1)デイーゼル車
1970年代後半からのディーゼル化進行の最大の要因はこの時期ガソリン税を大幅に引き上げて軽油との販売価格差を拡大した国の政策にあった。この政策は産業政策としてなされたものであったが、環境に対しては深刻な影響をもたらすことは明らかであった。このようなディーゼル優遇政策をとる以上、国は公害発生を防止するため、ディーゼル車に対する排ガス規制の強化などの施策を採るべき義務があった。ところが被告国は以下の通り現状追認的な後追い規制しか課してこなかった事実が審理の中で明らかにされている。
a.副室式エンジンのトラツク、デイーゼル乗用車などについては、多くのメーカーが到達したNO
x排出レベルを数年遅れで規制値としてきた事実
b.公害被害はますます拡大していたにもかかわらず、昭和57年・58年から昭和63年にかけて、ディーゼルトラック規制強化は根拠もなく中断された事実
c.ディーゼル乗用車には、ガソリン車よりも緩いディーゼル車独自の規制が課された(しかも、昭和61・62年規制まではディーゼル重量車等と同じ規制値であった。)ため、さらにディーゼル化が進むこととなったこと。
d.PMについては、1960年代から呼吸器疾患の原因となることや発ガン性等が知られていたにもかかわらず、平成5年・6年まで無規制の状態であったこと。我が国のPM規制の開始は、粒子状物質の環境基準ができてからなんと21年、アメリカのPM規制開始と比べても10年以上遅れており、東京都からも「決定的に立ち後れた」(東京都「環境白書2000」)と批判されている。
(2)ガソリン車
a.ガソリン乗用車:昭和51年規制の延期
当初昭和51年に予定されていた規制値が、規制対象業界である自動車工業会が加わった専門委員会により(規制強化を求めていた自治体や市民代表は加わっていない)、昭和53年まで延期されてしまった。しかし、当時の技術水準では、昭和51年に規制を実施することは十分可能であった。
b.ガソリン乗用車:昭和53年規制後技術的なレベルは年々上がっていったにもかかわらず、平成12年に至るまで規制強化がなされなかった。
(3)自動車排出ガス試験排ガス試験において使用されている走行モードが東京都内における実際の自動車走行状態から極めて乖離していること、排ガス低減装置の劣化が懸念される使用過程車が無規制のまま放置されていることなど、多くの問題点がある。
(4)諾外国の規制
諸外国と比べても、わが国の規制は甘い(特に平成5・6年にやっと設定されたPM規制値)。例えばディーゼル重量車に対するPM規制を見ると、下図のとおり、2000年における日本の規制値はEUの2.5倍、アメリカの2倍弱など、諸外国と比較して一貫して緩い基準となっている。
5 排ガス規制「談合」の構図(どうしてまともな規制が行われてこなかったか)
(1)メーカー言うがままのお手盛り規制
排ガス規制の規制値、実施時期などの決定は、規制を受ける側であるメーカーの白己申告によって事実上決まってしまうシステム中公審(中環審)の専門委員会には、メーカーが提出した技術資料を、専門的・技術的視点から批判的に検討する体制がない。
*カリフォルニア州の環境保護局は排ガス低減対策の専門スタッフ300人
(2)しかもメーカーが国に提出した「技術資料」は徹底的に秘匿。
・裁判の中で若干の資料が提出→前述のいすゾの資料(輸出車とのダブルスタンダード)などの他、「PM規制先送り問題」などが発覚米国1982年のPM規制開始の動きを受けて、被告国も80年頃からPM規制実施を目指して様々な調査、資料収集を行った。
→報告書も作成されたが、突然PM規制の実施は見送りとなり、それらの報告書は、裁判で請求されるまで非公開とされていた。
⇒メーカーサイドからの働きかけ疑惑が濃厚
I 従来の裁判例(道路管理者の責任)
| 西淀川2〜4次(1995.7.5) |
期問を限定(1971〜1977)し、特定道路(国道43号線、阪神高速大阪池田線)との関係で道路管理者の責任を認め、沿道50メートル以内に居住する患者に対する損害賠償を命じた。 |
| 川崎2〜4次(1998.8.5) |
道路網(国道1号線、同15号線、同132号線、同409号線、首都高速横羽線及び関連道路(市道))との関係で道蕗管理者の責任を認め、沿道50メートル以内に居住する
患者に対する損害賠償を命じ、さらに被害が現在進行形であることも認めた。 |
| 尼崎(2000.1.31) |
特定道路(国道43号線、大阪西宮線)との関係で道路管理者の責任を認め、沿道50メートル以内に居住する患者に対する損害賠償を命じた。 |
| 名古屋南部(2000.11.27) |
特定道路(国道23号線)との関係で道路管理者の責任を認め、沿道20メートル以内に居住する被害者に対する損害賠償を命じた。 |
Ⅱ 東京大気汚染公害訴訟の特徴
104路線の被告道路によって本件地域に網の目のように張り巡らされた道路網の暇漉を問題としている
被告道路国道13路線
首都高速道路19路線
都道72路線
Ⅲ 道路管理者の責任の内容
1 調査義務に違反した
環境アセスメントなど道路を設置・供用することにより沿道や周辺地域の環境に与える影饗(交通量の増加や大気汚染の悪化)の調査を怠った。
2 自動車交通需要が増大するに任せ道路を設置・拡幅して人口が密集している本件地域に大量の自動車交通を集中させた。
【本件地域の自動車交通量】(全国道路交通情勢調査による)
|
S33 |
S40 |
S46 |
S52 |
S58 |
H2 |
H9 |
| 国道 |
187,990 |
345,717 |
393,455 |
402,208 |
403,612 |
379,482 |
389,539 |
| 都道 |
435,866 |
1,110,404 |
1,463,079 |
1,346,583 |
1,347,282 |
1,297,336 |
1,294,731 |
| 首都高 |
|
|
533,405 |
425,972 |
411,411 |
622,443 |
682,078 |
| 合計 |
623,856 |
1,456,121 |
2,389,939 |
2,174,763 |
2,162,305 |
2,299,261 |
2,366,348 |
*全国道路交通情勢調査で首都高速道路の交通量調査を開始したのは昭和46年〜
3 道路公害対策の中心となる交通量抑制策を怠った。
個々の自動車の排出ガス対策が進んでも、自動車交通量が増加を続ければ大気汚染の改善は不可能であるから、自動車交通量そのものを抑制・削減することにより、排出される白動車排出ガスの総量的削減を目指す交通量抑制策(ロードプライシング、走行ルート・レーン規制等)が道路公害対策の中心である。東京都は、ようやく2000年8月からロードプライシング導入にむけて検討を始め(ロードプライシング検討委員会)、200!年6月には実施に向けた報告書が作成された。
Ⅳ 争点
1 自動車交通需要は制御可能か
被皆らの主張:交通需要は基本的に国民の自由な社会・経済活動から生じる自然発生的なものであり、道路管理者がこれに対応して道路を設置管理していくのはむしろ自然公物の管理に類するもの…
←本件地域への交通需要の集積は、膨大な人口と人間の杜会的経済的活動が本件地域に集中したこと、すなわち被告らが、都市の無秩序な膨張、人口の集中を抑制し、居住環境を保全し暮らしやすい都市の形成を目指すことが基本的な理念とされる都市政策を誤ったことによって引き起こされたものである。
2 道路の公共性
被告らの主張:道路は、極めて多面的な機能を発揮し、国民の日常生活や経済活動に欠かすことのできない最も基本的かつ重要な公共性を有する杜会資本であるから、被害が生じたとしても受忍すべきである。
←単なる生活被害を超える生命、身体への危害という極めて重大な権利侵害が存在していながら、なおその損害が受忍限度の範囲内であり、これについての損害賠償をも許さないとすべき高度の公共性があるとまでいうことは到底できない(名古屋南部)。
3 新たな幹線道路の整備が渋滞の緩和や自動車排出ガス排出量削減に不可欠か被告らの主張:自動車の交通流を円滑にすることにより、交通渋滞が緩和され、排出ガスの排出量削減につながるのだから、遅れている都市計画道路の整備、高規格幹線道路のネットワーク整備を押し進める必要がある。
←交通流を円滑にする交通流体策は、効果的な交通量抑制策が同時に実施されて、はじめて排出ガス排出量削減の効果を生じる。また、幹線道路の建設が、誘発交通を生み出し、自動車交通量を増加させることは、イギリスにおける調査によっても明らかとなっている(r幹線道路と交通の創出」(TrmヒRoadsandtheG㎝crationofTraffic)、1994年5月)。
Ⅰ 従来の裁判例(自動車排ガスの因果関係)
|
一 般 |
沿 道 |
| 西淀川1次(1991.3.29) |
× |
× |
| 川崎1次(1994.1.25) |
× |
× |
| 西淀川2〜4次(1995.7.5) |
○
但〜S52
SO2と相加影響 |
○
S53〜もN02+SPMで影響あり
但,受忍限度内で違法性ナシ |
| 川崎2〜4次(1998.8.5) |
○
S50〜もm沖心に影響あり
但,沿道50m以遠は,受認
限度内で違法性ナシ |
○ |
| 尼崎(2000.1.31) |
× |
○ |
| 名古軍南部(2000.11.27) |
× |
○ |
Ⅱ 本件裁判のポイント
沿道についての因果関係は当然として,一般環境についての因果関係が認められるかどうかが,最大のポイント
Ⅲ 一般環境の因果関係
1).最新の知見(尼崎・名古屋訴訟にも未提出で,東京で初)
(1)米国・カリフオルニアのAdventist Hca1th Study
・1Oないし15年間,同一対象者(6340人)を追跡調査
・一般環境の大気中粒子と喘息・慢性気管支炎などの発症・増悪との間に有意な関連がくり返し認められた。
・SPM換算24h値で32〜100μg/㎡をこえた回数との間で有意な関連が認められており,これは本件地域でも十分認められる汚染レベル。
(2)欧米の短期影響研究
・一般環境のNO
2あるいは大気中粒子濃度の上昇にともない,ぜん息等による死亡,入院,救急治療室利用,気管支拡張剤の使用,往診などが増加するとの有意な関連を見出した肝究が多数蓄積。
(3)千葉大調査・暴露評価研究
・尼崎・名古屋判決が援用した千葉大調査の一連の研究で、2001年に発表(東京訴訟で初めて提出)。
・一般測定局のNO
2濃度が高い地区ほど,ぜん息発症率が高く,0.1ppmあたりの発症危険が2.1倍と明確に有意な関連が認められた。
2.加えて
千葉大調査(尼崎・名古屋判決援用分)
尼崎・名古屋判決
都市部一般に対し,都市部沿道の2倍の発症危険は自動車由来の粒子状物質の影響として因果関係肯定。
しかし,田園に対し,都市部一般の2倍の発症危険が,同じく自動車由来の粒子状物質の影響がどうかにつき判断脱漏'これはまさに都市部一般環境における自動車排ガス汚染との因果関係を裏づける知見
cf.尼崎判決
「2倍の発症危険は,集団的因果関係を肯定するのに参考になる値」
3.従来の疫学的知見
一般環境大気のN0
2,(SPM)とぜん息、慢性気管支炎の有症率,発症率との有責な関連を認める疫学的知見が蓄積されている。
①岡山調査
②6都市調査
③環境庁a,b調査
④環境庁継続調査(91年報告,97年報告)
これらは一般環境におけるNO
2SPM)を指標とする自動車排ガス汚染とぜん息等の因果関係を裏づけるもの
4.米国EPAの微粒子(PM2.5)規制
(1)微粒子影響に関する知見
①微粒子高濃度地域は,低濃度地域に比べ,死亡率高い(ポウプら,ドッケリーら)
②微粒子濃度の変化と日々の死亡率との間に,有意な関連あり。
(2)米国EPAでは,1997年7月から,新たな微粒子規制を実施
基準は,
PM
2.5 年平均 15μg/㎡
日平均 65μg/㎡
cf.本件地域(換算)
区部平均 36μg/㎡
練馬(一般局) 46μg/㎡
大和町(自排局) 66μg/㎡
5.実験的知見
(1)ディーゼル排出微粒子(DEP)によるアレルギー反応の促進
①花粉症研究
②喘息研究
(2)国立環境研,嵯峨井らの研究
DEPによりぜん息の基本病態発現
ディーゼル排気とアレルゲンの併用投与でぜん息病態の発現,悪化
Ⅳ 幹線沿道の因果関係
1.千葉大調査
沿道は,都市部一般の2倍,田園の4倍の発症危険
2.都内沿道調査
都内沿道,非沿道を対象とした疫学調査で,くり返し,沿道において有症率が高い結果が見出されている(名古屋判決でも援用)
3.海外の調査
英国,オランダ,ドイツ,イタリアで交通量(とりわけトラック)が多いほど,ぜん息,その他有症率が高いとの結果が見出されている。
I 東京大気汚染訴訟の特色
1,多数の道路を裁判の対象としていること
(これまでの裁判例)
・西淀川
対象は、国道2本(2号、43号)と岐神高速2本(大阪西宮線と大阪池田線)
認容は、国道43号線と大阪池田線の2本の道路の沿道50mかつ、期間を昭和52年までに限定(いわば「線的」な認定)
・川崎
対象は、国道4本(1号、15号、132号、409号)と首都高1本(横羽線)
認容は、これらの道路と共に多数の県道・市道との共同不法行為を認定。ただし、道路から50mに限定(いわば「網の目状」な認定)
違法な加害行為が現在も継続していると認定
・尼崎
対象は、国道2本(2号、43号)と阪神高速1本(大阪西宮線)
認容は、国道43号線と大阪西宮線の2階建て道路沿道50m(いわば「線的」な認定)
違法な加害行為が現在も継続していると認定
・名古屋南部
対象は、国道4本(1号、23号、154号、274号)
認容は、国道23号線の沿道20m(いわば「線的」な認定)違法な加害行為が現在も継続していると認定
(東京大気訴訟の被告道路)
国道13路線
首都高速道路19路線
都道72路線
2,対象地域が広いこと
(先行訴訟)
・川崎(川崎区・幸区の2区)50.34km
2
・西淀川1区14,23km
2
(東京大気訴訟)
23区616.18km
2
3,別紙図面参照
Ⅱ 争点
1,汚染の深刻さの捉え方
(原告)
NO
x,SPM(PM
2.5)にっいて我が国で最も深刻な大気汚染が継続している。尼崎判決で差止基準とされた日平均値0.15㎎1m3と対比すると、本件地域の汚染濃度は、一般局でもこの差止基準を超過しており、たとえば、平成7年においては本件地域の全ての一般局でこの差止基準を超過している。
2,汚染の到達範囲
(被告ら)
幹線道路からの大気汚染物質は、道路から離れることにより急激に減衰しており、道路から(20m程度)離れた地点にはほとんど到達していない。
(原告)
・東京都の実施した各種の調査(シミュレーションおよびCMB法)によれば、N0
2汚染については自動車の寄与が圧倒的な比率を占め、幹線道路だけで50%を大幅に越えるており、SPMについても、自動車排ガスの寄与は、SPM全体48%、微小粒子では56%に達する。これらは、道路から離れた一般環境の値であり、本件地域内に多数の幹線道路が網の目状に配置されていることの結果として、道路から排出されたSPM,N0
2が道路沿道から離れた後背地も深刻に汚染し、地域全体を面的に汚染している。
皿 立証
(原告側)
・東京都が行った汚染実態の測定及び東京都が汚染寄与を解析した各種の調査(シミュレーションおよびCMB法)
・環境総合研究所青山証人によるシミュレーションの実施(証人尋間)
なお、証拠の構造の観点からは、従前の裁判例との対比でいうと、「線的」な認定にとどまる、「西淀川」、「尼崎」、「名古屋南部」はこうしたシミュレーションによる立証を行っていないのに対して、同じく青山シミュレーションを実施した「川崎」においては、地域内の多数の道路による共同の汚染を認めている(「網の目状」)ことが注目される。別紙のカラー図のシミュレーション結果参照。
(被告側)
特別の証人は立てなかった。
I 問題の所在(差止の必要性)
過去の損害の賠償が認められるだけでは全ての解決に至らない。これまでの汚染環境を改善しなければ、症状の増悪により患者の被害が継続するばかりか、新たな患者の発生により被害が拡大することとなる。特に、すでに発病し大気汚染に対しとりわけ感受性の高い社会的弱者たる原告らが、緊急に大気汚染物質の差止を求める必要性は大きい。そして、全ての生物の共有物たる大気を汚染した者にこそ、その改善の義務が課されるべきである。そのため、原告らは被告らに対し、損害賠償請求に加えて汚染物質の差止を請求している。
Ⅱ 原告らの請求(訴状請求の趣旨一」)
「一、被告らは各自、
1、被告国、同東京都および同首都萬速道路公団は、別紙道路目録記載の各道路を自動車の走行の用に供す'ることにより、
2、被告会社らは、その白動車を製造・販売して、東京都23区内の各道路を走行させることにより、それぞれ排出する左記(下記)の物質につき、別紙原告目録一ないし七二、同七四ないし八一、及び同八八ないし一○二の原告らの居住地において左記(下記)の数値をこえる汚染となる排出をしてはならない。
| 物質 |
数値 |
| 二酸化窒素 |
1時問の1日平均値0.02PPM |
| 浮遊粒子状物質(粒径10ミクロン以下のもの) |
①1時問の1日平均値O.10mg/㎡
②1時間値O.20㎎/㎡ |
Ⅲ 従来の裁判例
1 西淀川1次(1991.3.29) ×(不適法として却下)
2 川崎1次(1994.1.25) ×(不適法として却下)
3 西淀川2〜4次(1995.7.5) ×(抽象的不作為講求は適法であるものの、環境基準は差止基準として合理性がないとした)
4 川崎2〜4次(1998.8.5) ×(抽象的不作為請求は適法であるものの、環境基準は差止基準として合理性がないとした)
5 尼崎(2000.1.31) ○(浮遊粒子状物質につき1時間値の1日平均値0.15mg/を超えてはならない)
→ただし、原告・企業問では和解が成立したため、判決は国および阪神高速道路公団に対するもの
6 名古屋南部(2000.11.27) ○(浮遊粒子状物質につき1時問値の1日平均値0,159皿g/を超えてはならない)
→ただし、国に対するものW差止請求の法的根拠差止講求が認められるかについては、従来学説上も裁判上も争いがあった。しかし、判例の積み重ねにより以下のような論点はクリアされ、差止請求が法的に認められることについては現在ほぼ争いはない。
Ⅳ 差止請求の法的根拠
差止請求が認められるかについては、従来学説上も裁判上も争いがあった。しかし、判例の積み重ねにより以下のような論点はクリアされ、差止請求が法的に認められることについては現在ほぼ争いはない。
1 憲法上の根拠
(1)人格権
憲法13条及び25条が保障する人格権(生命や健康を脅かされない人格的利益)を実現するために、民事訴訟手続として差止講求が認められる。
→公害被害について人格権を根拠として差し止めうるという考え方は、いまや学説・判例上定着している。近時の尼崎・名古屋南部判決も
同様である(ただし、尼崎判決ではr身体権侵害に基づく人格的講求権」と表現している)。
(2)環境権
さらに、憲法13条及び25条が保障する環境権(良好な自然環境を享受し、これを保全する権利)も根拠となると考えるべきである。なぜなら、自然環境は地域の現在及び将来世代の住民が享受すべき公共物であり、そ
の破壊は現在の一個人の人格的利益のみならず将来世代の人格的利益(人格権)を侵害するおそれがあるからである。
→判例上未だ明確に認めたものはないが、環境権的発想のもとに差止請求を認めたいくつかの下級審判決がある。学説でも新しい人権の一つとして議論されている。
2 被告国に対する請求の司法判断適合性
原告らは民事訴訟により差止請求を求めているが、被告国に対して行政規制権に基づく公権力の行使を求めるものではなく、あくまでこれと抵触しない被告国の行為による差止の実現を求めている。したがって、その実現内容は行政権の発動・行使を強制し、行政事件訴訟(義務付け訴訟)であるから司法判断が許されないとする批判はあたらない。
3 被告メーカーらに対する差止の実現可能性
被告メーカーらは、蔽後に製造・販売する自動車について低排出車へのシフトを行う、既に市場に供給された白動車にDPF装着するなど、汚染物質排出回避の措置をとることができる。よって、原告らの被告メーカーらに対する差止講求は実現可能性がある。
4 その他
差止請求が、汚染物質を排出しないといういわば抽象的な不作為を求めるものであることから、請求の趣旨として特定しているか、給付条項として明確か、強制執行の可能性あるか、などの論点も存在するが、それらがクリアされることについては、尼崎・名古屋南部判決においてもすでに自明の理となっている。
V 差止の具体的基準(原告らの請求する具体的基準の妥当性)
差 止請求が法的に認められることを前提に、具体的にいかなる基準を定立するかについては、原告らは第2で示したような基準が妥当であると考える。 その根拠は、以下のとおりである。
1 環境基準と同値
原告らの求める基準は、環境基準(二酸化窒素については1973年の旧環境基準、浮遊粒子状物質については1970年設定の現環境基準)の数値と同一である。このことからも、健康被害を防止するための必要最小限度の濃度条件たる基準であるといえる。ただし、原告らは環境基準として設定されたことのみを理由として差止基準たりうると主張するものではない。2項で述べるように、あくまで科学的根拠をもとに基準を定立している。
2 科学的根拠
被告らの排出する大気汚染物質は多種多様である。しかし、原告らは1日も早い有害物質の規糊を求めるため、現在の科学的知見において人体への健康影響が明白な二酸化窒素・浮遊粒子状物質に限定して差止を求めている。
(1)二酸化窒素について
千葉大調査、岡山県調査、6都市調査を統計的に処理分析すると、単純性慢性気管支炎の有症率が有意差をもって上昇するNO
2年平均値は、O.014〜O.017ppm≡となる。また、環境庁a,b調査(1986年)によっても、0.01〜0.02ppm超の地域では、それ以下の地域より有症率が高い傾向が認められている。
ただし、これらの疫学調査は実験対象の安定性を確保し、反応のばらつきが激しい弱者群を排除するために調査対象の均質化を図っている(例えば、40才〜60才の男女0)群に限定している)。そこで、大気汚染に対し感受性の強い小児、老人、病人等の弱者保護のためには、一般に人の標準偏差が0.2〜0.3程度であるとされていることからして、平均的な50%の人に髭響がない濃度条件の約1.6〜2分の1、 すなわち安全係数2を見込むことが必須となる。よって、原告らをはじめとする本件地域住民の大気汚染による健康被害を防止するためには、安全係数2を乗じた年平均値0.01ppm(年平均値と日平均値の98%値とはほぼ1対2の関係がみられるので、日平均値に換算すると0.02ppm)こそが必要最小限の差止基準となる。なお、この数値はこれ以上の濃度であれば安全とはいえない、即ち危険であることが証明された(危険の証明)にすぎない。よって、これ以下であれば危険ではない、即ち安全が証明された(安全の証明)わけではない。
(2)浮遊粒子状物質について
1970年の浮遊粒子状物質環境基準設定の際の1970年12月付厚生省生活環境審議会公害部会浮遊粉じん基準専門委員会報告に根拠としてあげられた知見や、環境庁a,b調査(1986年)、千葉大調査等によれば、年平均値100μg/㎡(0.10mg/1㎡)の濃度条件下で呼吸器症有症率が増加する。これに必要最小限の安全係数2を見込んで得られる年平均値50μg/㎡(日平均値に換算すると0.10mg/㎡)が健康被害を防止するための必要最小限の差止基準と言うべきである。さらに、短時問高濃度曝露により病弱者、老人の死亡率が増加することを配慮し、前記濃度条件に対応する1時問値200μg/㎡もあわせて必要最小限の差止基準と考えるべきである。
IV 最も原告らが訴えたいこと
現在東京23区内全域の汚染濃度は、原告らが求める差止基準を大きく超過しているうえ、尼崎・名古屋判決の差止基準をも上回っている状態にある。原告らは、白らの被害の回復とともに、排気ガスを少なくして欲しい、自分のような辛い思いをする患者宇1人でも少なくして欲しいということを必死に望んでいる。

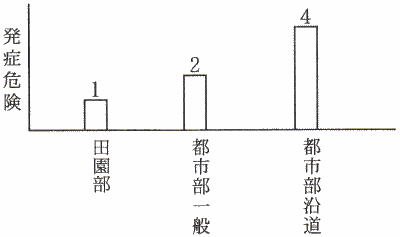
![]()